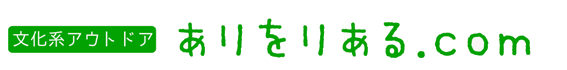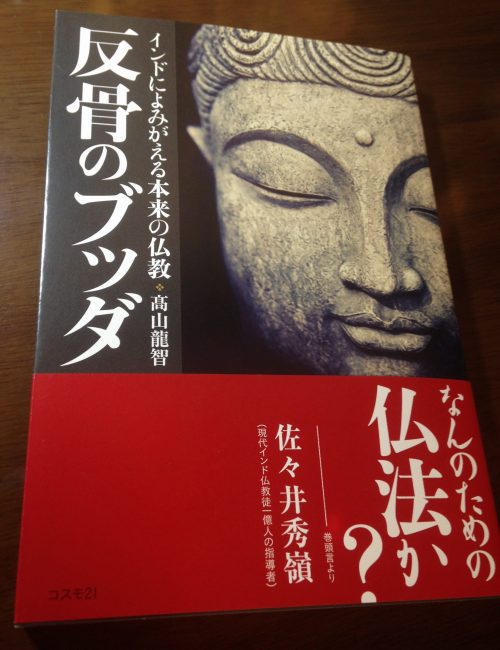翻訳すると、当然生じる違い
2500年前を生きたブッダの言葉を、弟子たちがまとめたのが初期仏典なわけですが、それらはサンスクリット語やパーリ語で表記されています。
日本でも、中村元先生のような偉大な仏教学者が初期仏典を翻訳してくださってますので、私たちも読むことができるわけですが、単純にそれらを読むだけでも、ブッダが言っていることで感じる印象と、なんとはなしに仏教に対して持っていた印象が違うことに気づきます。
私が読んだのは、本当にその一部にすぎませんけども(その限られた経験で物を言うのはどうかと思いますが)、ブッダは、ものすごく合理的で、謎めいたことを言わない人だったような感じがするんですよね。
確かに、翻訳ものを読むと、原本と大分印象が違う、なんてことはよくありますよね。翻訳した人の解釈や翻訳言語の特性、文化的個性が、どうしても出てしまうからでしょう。仏典は、サンスクリット語やパーリ語の仏典を、中国で漢字に翻訳したものが日本に到来しているものがほとんどですから、原典とだいぶ違くなってるだろうということは、想像に難くないわけです。
さて、本書で高山さんは、その感覚をもう一歩進めよう、とおっしゃいます。
時代は変わった。
サンスクリットやパーリ語もヒンディー語ととても似ているので、翻訳機を使えば解読だってできる。つまり、原典を直接読むことだって可能なんだよ、と。
「原始仏教ではなく、『言語』仏教へ」
「仏教経典を記述したパーリ語やサンスクリット語は、インドの公用語たるヒンディー語と流れを同じくする言語であり、インド人でも多少の学習は必要となるが、現代日本人が『枕草子』を理解するよりはずっと垣根が低いと言える」(P22より引用)
このくだりを読んで、思わずおおおお!?と声を上げてしまいました。
そのくらいの段差?!たいして遠くないですよ?!
日本語でも、古語にしかない言葉もありますが、今も昔も変わらぬ言葉もあります。あるいは、使い方や意味が、時代によって違う言葉もありますね。
わからない言葉もあるけど、なんとなくわかります。
例えば、「サンガ」という言葉。
ヒンディー語を母語としている人は、この言葉は「共同体」という意味の言葉なんだそうです。宗教的な言葉というよりも「団体」といった意味で今も使われるごくごく一般的な言葉。
ところが、古い時代に、漢字では音訳として「僧伽」とし、意味合いとしては「侶(パートナーの意味)」で補って「僧侶」と翻訳。これで、「共同体」という意味と音を表現したわけなんですが、日本ではそれがいつの間にか一人の出家者のことを指すようになっています。
この言葉ひとつとっても、だいぶ印象が違いますね。
最も基本的な言葉でさえ、そんな感じなわけですから、膨大な言葉で形成されている経典では推してしるべしです。
「仏教」とは一体何なのか
本書を拝読すると、ブッダが生きた時代やインドならではの文化的状況を背景に感じながらも、素直にその言葉の意味を知ることでもって、ハッとさせられます。
しかし、ブッダの死後、何百年もたってインドを遠く離れ、いろんな環境の中である意味「異常発達を遂げた」仏教の枝葉について、どう考えたらいいんだろう、と戸惑いを覚えずにはいられません。
長い歴史の中で、各地・各時代の偉人が格闘して得てきた果実が、もしブッダの言っていたことと異なることであっても、それはそれでやっぱり大切な宝物なのではないのかな、と思います。
私のポンコツ頭で考えてもよくわからないのですが……
そうして格闘し、のたうち回って真理に近づこうとするそのフロー自体が、最も大切なことなのかもしれないな、と思います。そんな種を、ブッダは世界中に蒔いたんだ、と。
本書の中で、高山さんがブッダが説いたことをこんな風に言っておられます。
「問題や悩みがあれば、自分で解決する人になればいい」
「人類同士が、隣の人との友愛によって、自ら救済されよ」
私はそれを自分ふうに言い換えて、胸に刻んでみました。
誰かに救ってもらうのではなく、自ら救うのです。
隣の人のために何かしようと思う気持ちが力になって、自分を救うのです。
……どうしたらいいのかわからない、と思いながら日々生きておりますが、
そんな言葉を土台に、日々を重ねていきたいと思います。
(むとう)